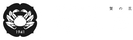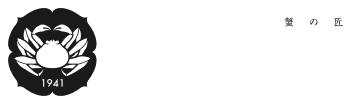柴山がにが“活きる”まで──。
11月7日初競りが始まる

日本海は、夏の鮮やかな青から、深く沈むような青灰色へと変わっていきます。
風は次第に冷たく、海面は重たく、波の白が際立つ季節。
11月初頭。
吐く息が白くなるころ、ここ兵庫県香美町・柴山漁港では、冬の訪れを告げる柴山ガニ(松葉ガニ)漁の最盛期が幕を開けます。
夜明け前、漆黒の海にゴウゴウというエンジン音が響き渡り、ひとつ、またひとつと漁船のライトが光の筋を描きながら港へと帰ってきます。
冷たい潮風の中に、エンジンの熱気と人の声が交わり、静まり返った夜の港に、命の営みが灯る瞬間です。
初競りの日――。
夜明けとともにすべての漁船が港に集まり、漁港は一変して喧騒の渦に包まれます。
荒々しい掛け声、動き回る人々、白い息が舞う空気。
冬の日本海が最も熱い瞬間です。

柴山漁港最大の特徴と言われる厳しい選別。
水揚げされた柴山ガニ(松葉ガニ)は大きさ、姿形の良し悪し、色艶で仕分けられます。
その仕分けランクは驚くことに100以上。
仕分けは真夜中12時から翌6時まで行われ、漁港場内に整然と並びます。
その緻密で繊細な仕分けは日本を越え世界一といわれます。

ピンク色のタグは良質な松葉ガニの証、この厳選なランク分け作業をすることで柴山ガニは品質と信頼において最高峰のブランドガニとなっています。
早朝になると、さらに柴山漁港は活気づきます。
柴山がにの美味しさと魅力を知り尽くした蟹のプロである仲買人が、より良い柴山ガニ(松葉ガニ)をお客様に届けるため場内に集まるのです。
カネニもそのひとり。目利きが競りに挑みます。

柴山漁港の競りは欲しいものの価格を競り札に書き、一斉に挙げ、一番高く値をつけた仲買人がおとせる方式。
競り札に書いたそばから、軍手でぬぐい消し、また次の競りに挑む。
この繰り返しが長いときには正午まで続くそう。
目利き10年、茹で一生
目まぐるしい競りで落とした柴山ガニ(松葉ガニ)は漁港内にあると言っていいほどの距離のカネニ工場に移動します。

創業以来80年、三代に渡って引き継いだ”目利き”の職人技はカニの微妙な違いを眼力と触感で見極めています。
なぜならカニは100g違えばもちろん、50g違うだけで甲羅の大きさや身入りが全く異なります。
それもそのはず、柴山ガニ(松葉ガニ)は成長が遅く成体になるまで10年〜15年かかるそう。
このじっくりとした熟成とも言える成長の遅さが50gの違いを際立たせているのです。

そしてその目利きから預かる柴山がにを仕上げるのが”茹での職人”。
かに界隈の格言に『目利き10年、茹で一生』というものがあり、それだけ、最高の状態に完成させる”茹で”の行程は難しいものとされています。
カネニのベテラン職人が、いかに鮮度を守るか、いかに旨味を引き出すか、
いかに最高の茹でを完成させるか。釜の中で、赤く染まっていく柴山がにと真剣勝負に挑みます。
こうして海底200〜500mの厳しい自然環境で育ったカニは、カニに携わる様々な職人の元を経て”美味しい”芸術品として柴山がに仕上げられるのです。
柴山ガニ(松葉ガニ)の漁期は11月7日〜3月末頃まで。
柴山の味覚、冬の味覚の王様”柴山がに”。旬を旬のうちにご賞味ください。

柴山がに活姿【冷蔵】
活ガニ(生)とは水揚げされたままの状態です。
活ガニには「柴山がに」のタグ『ピンク色』をつけるように定義づけられています。

柴山がに茹姿【冷蔵】
茹姿とは1匹そのままを自社工場の釜で塩茹でしたものです。
活ガニには「柴山がに」のタグ『ピンク色』をつけるように定義づけられています。